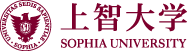更新情報Updates
逸見シャンタール先生にインタビュー

ストーリーも絵も自作の紙芝居(後ろの棚にも飾られている)。
小児病棟やチャリティイベントなどでボランティア上演。Festival UK ‘98の作品。
英語教育の逸見シャンタール(Hemmi Chantal)先生の研究室には、以前から優しい色彩の自作紙芝居が飾られていました。3月に本学をご退職になるタイミングで、上智での英語教育から、ボランティアで演じた英日語紙芝居のことまで、インタビューの機会をいただきました。
I. 素材と対話し、考えを深める英語教育
――英語教育で大事になさっていることは?
言語を使ってそれぞれの学生が自分の思いを伝えたり、考えを深めていったりすることが、上智の英語教育で行っているCLIL(内容言語統合型学習)という手法の大切な一面です。ですので、学生さんがどなたも平等に、話のターン(順番)があって、そのご意見が非常にユニークなものだったり、他の方と違ったことでも、まず受けとめて、そして、その方のカラー(個性)がお話の中に出てくるように促します。どんな発言に対しても、決して「まちがい」という捉え方はせず、「今おっしゃったことについて、私はこういうふうに思ったのだけど、どう思う?」といったふうに、その方の考えを引き出すことを一番大切にしています。
――自分をオープンにして話すことは難しかったり、英語を使って話すことに慣れていなかったりする場合もありますよね?
はい。英語が得意と思っている人も、そうでない人もいます。ちょっと得意でないなと思っている学生さんも、自分のもっている言葉を使って、自分の考えや思いを伝えられるように促しています。
――そのためのよい教材や、特別な極意がありますか?
教材はよいものがたくさんあり、上智の必修の科目でも取り入れているような使いやすい教材はありますが、特別な教材があるからいい授業ができるという考え方はしていなくて、まずそこに学生がいて、教材という素材を使ったときに、学生たちがその素材とどう対話するだろうというような発想で、授業をデザインしています。
――「素材と対話する」とは?
「主体的・対話的な深い学び」という表現が文部科学省の新しい学習指導要領の文献(※1)に、授業改善の姿勢として表されています。大学生が読む、文字で書かれた本であっても、それを読むときの自分の解釈と、そこに書いてあることとの対話が生まれると思うのですね。また教室では、これはこういう意味かな、ああいう意味かなと考えるとき、自分が知っている世界をそこに持ってきて、解釈をしていくと思うのですけれども、私が一番面白いと思うのは、みんな同じテキストを使っていても、それぞれのもっている知識とか経験とか興味が違っていますので、どのくらいの英語で自分の解釈を表せるかということも探りながら、必要な知識を学んだり、その場にいる学生同士でお互いに教え合ったりして理解を深めていくことになります。そのような学生と素材との対話が、どのように生まれるかということを常に意識しています。
(※1)文部科学省国立教育政策研究所(n.d.).学習指導横領を理解するためのヒント(n.d.)
――先生の授業は、授業の中の読む・聞く・見る・話す…様々な場面で生まれる「対話」を基本にするものなのですね?
そうですね。「対話」というと言葉を発するようなイメージもありますけれど、黙っていても頭の中で色々なことを思っている場合もありますから、それも含めての対話ですね。上智の1年生の必修では、秋学期はCLIL(内容言語統合型学習)の手法で、内容と言語を統合させて、その中で言葉を覚えていきます。大学での学びですので、ただ流暢な英語で話せるように、書けるようにということではなく、適切な文献や、信憑性のある素材を使って、それらに興味をもって勉強しながら、そこで必要な言語を教えていくという考え方です。CLILでは4つのCという原理を大切にしており、Content(内容)、Communication(言語)、Cognition(思考)、 Community/Culture(コミュニティーあるいはカルチャー)(Hemmi & Banegas 2021 ※2)を取り入れてプログラムおよび授業作りをして行きます。その中で「対話」を大切にして知識及び言語の構築を、批判的思考を取り入れながら行って行きます。
(※2)Hemmi, C. & Banegas, D. L. (2021) CLIL: An Overview. In C. Hemmi, & D.L. Banegas (Eds.). International Perspectives on CLIL, 1-20. Cham: Palgrave Macmillan.
――春学期のEAP (English for Academic Purposes) の授業は、どのように進めるのですか?
まず前期の必修授業では、「学習スキル」といって、技術的なことを学ぶことがメインになります。英語で何かのテーマを学ぶ際に必要な、リーディングの技能、リスニングとメモの取り方のこつ、プレゼンの行い方、エッセイのプランニング、パラグラフライティングなどについて学びます。後期は、内容主導になっていき、そこで使う言語を学んで行きます。
――CLIL(内容言語統合型学習)で取り上げるテーマは、それぞれの先生が独自に選ぶのですか?
そうです。それぞれの先生自身の専門、学生の興味、現代社会の問題などから、様々な観点でテーマを設定します。私は、博士論文でアイデンティティに関するテーマを扱ったのですが、自分のクラスでは、イギリスのDiversityとIdentityを取り上げたり、最近はDX (Digital transformation, デジタル技術による変革)を取り上げてみたり、色々なことをテーマにしてきました。文献を読んで、自主的にリサーチクエスチョンを立て、グループワークで調査し、クリティカル・シンキングをし、発表する、というプロジェクトに取り組んで参りました。最近ではCOIL (Collaborative Online International Learning) を取り入れてアメリカのノースキャロライナ・シャーロット校と自分のクラスをズームで繋ぎCLILのコミュニティーを広げる工夫をしております。COILの魅力は日本で勉強する学生が日本にいながら海外の学生と繋がり、対話をすることができることです。
II. 自身のアイデンティティの中の英語、世界共通語としての英語教育
――言語教育と文化という観点でみると、英語は世界共通語としての側面と、英語を母語(第一言語)とする人たちの文化を反映する側面と、両面あると思うのですが、英語教育のうえではどのように捉えていらっしゃいますか?
私自身についていえば、英語は自分のアイデンティティと深く結びついています。9歳の時にイギリスに「外国人」として渡り、最初はでデイスクール、そして3年目は全寮制の学校で過ごしました。その頃には「外国人」ではなく、みんなの中の1人になっていました。小学校6年生の時に香港に移りましたが、イギリスでの体験は自分にとって今でも影響力が強いので、イギリスの「発音」とか、そういうものを個人的には大切に思っています。上智に来る前の18年間は、British Council東京校に勤めていたこともあり、日本に住みながらイギリスにいるような生活をしていました。私のアイデンティティの中では日本はもちろんのこと、イギリスはとても重要です。
ただ、現在の英語教育ということに関していえば、世界共通語としての英語、ELF (English as a Lingua Franca) という位置づけで英語を見ていますし、今は世界の英語教育の中でもその傾向が強いと思います。たとえば、20年以上前British Councilで教えていた頃から、イギリスの英語が好きで学びたいというよりも、世界の方々とコミュニケーションをするために英語を学びたいという希望をもつ学生が多かったように思います。現在のBritish Councilでもそのような捉え方をしています。上智で英語を教える時も、私自身はイギリスのアクセントが強いですが、意識して色々な文化・地域の方が英語で会話をするという場面を見せて、音や表現の特性の違いに目を向けたりしながら、世界共通語としての英語という面を強く出してきました。英語で書かれた英語の教材も、色々な国、分野のことが書いてあり、必ずしも一定の国や地域に根差した文化を反映しているわけではありません。
――学生の反応はいかがですか?
時々、学生たちは、「アメリカの発音でこの言葉を言ってみたいんですけど、先生、やってみてください」などと言うので、アメリカと言ってもいろいろな発音がありますが、「多分こうだと思う」と言って発音してみたりすると、その実践をとっても面白がって受けとめてくれたりします。この時にいつも笑いが起きます。私が下手だからでしょうか。そこから、人々の発音とアイデンティティということに結び付けて講義をしたり、イギリスの階級のピラミッドがよりフラットになってきていることや、ロンドンからテムズ河口に聞かれたEstuary English(河口域英語)(David Rosewarne 1984 ※3) がどんなものかとか、言語というのは人々の動きによって変化していくといった、現象としての英語を見たりもしています。それから、私はタイのNGOでボランティアに英語を教える活動を行ったことがありますが、タイ人とアメリカ人と日本人のスタッフの間でどのようなコミュニケーションの難しさがあったかについて学生に話すこともあります。そうしたところから、授業の課題として読んでいる文献などに結び付けていきます。学生の反応としては、自分自身の体験に基づいた解釈などを授業で発表することが多くあります。
(※3)Rosewarne, D. (1994) Estuary English: tomorrow’s RP?. English Today 37,10-1, 3-8. Cambridge University Press.
――Estuary English(河口域英語)について、もう少し教えていただけますか?
イングランド東南部の中産階級が話す英語で、これはイギリスの言語学者であるDavid Rosewarne (1984) の造語であります。多くの方がEstuaryを話している中、私はいわゆる昔の1970年代までのBBC放送で使われていた英語を話し、British Councilの私の上司は誇りをもってCockneyを話す方でしたので、2人がフォーマルな場でペアで話すと、その対比がユーモラスに受けとめられたりしたこともありました。たとえばWaterのtをGlottal stop(声門閉鎖)に変え、Estuaryの発音にして、親近感を与えるように調整するといった話し手の態度がみられることもあります。話し手が聞き手の英語に合わせる現象が起きていたのだろうと思います。人と人とがつながるときにこのようなことが起きることは興味深いと思います。
III. 日英語紙芝居の創作、ボランティア上演
――以前、先生のお部屋に飾られていた手描きの紙芝居についてお話をうかがえますか?
はい。私があの紙芝居を作った原点は悲しいという気持ちでした。1980年代後半にボランティアでタイに行った頃、自分の存在って何なんだろう?自分は誰なんだろう?ということを毎日考えていたのです。その答えが出ないことが悲しいと思っていました。私はChantalとNaokoという2つの名前をもっていますが、Hemmi Naokoをやっている時の自分と、Chantal Hemmiをやっているときの自分というのがかなり違うように感じておりました。言語も違うし、自分はどちらなのかな?両方なのかもしれない、などと考えていたのです。そういう発想で、存在と言語ということをいつも考えていた時、タイの宿でベッドと椅子と机しかない部屋でふと思いました。ベッドは大きなボードを載せたらテーブルになるし、椅子をつなげてクッションを置いたら赤ちゃんが寝られるベッドのようにもなるし、子どもが椅子を馬に見立てて遊ぶこともできる、もしかしたら、私も同じかもしれないという発見があったのです。修士課程で何を専攻するか迷っていましたが、興味のあるアートでもいいし、英語教育でもいいし、日本語教育でもいいし、自分がどのような人になっていくかは外的な要因もありますが、自分のチョイスだと思って日本に帰国しました。
そんな中で、紙芝居を作って好きなダンスと結び付けてみることもできるかもしれないとも思いました。でも、実際に行動に移すには勇気が要るし、怖いと思いました。その気持ちを変えられるかもしれないと思い、1日10分、とにかく絵を描いてみることにしました。それで、上手じゃないけど描き始めて、なんと18枚を描くのに5年もかかってしまいました。
――どういうストーリーですか?
ある猫が親と別れて都電に乗って色々な人々に会って成長していきます。親は地域のホームレス猫のために食べ物を探して旅に出ていくわけですが、最後に奇跡が起きて、旧約聖書の出エジプト記に記されているマナ(不思議な食べ物)が空から降ってくるというお話です。ソフィアというオペラシンガーに会って、神田の駅前でストリートパフォーマンスをする場面が出てきたりします。私の生徒だった形成外科医の方から、病院でそのパフォーマンスをしてみてはと勧められて、小児病棟の子どもたちに向けて演じることになりました。アーティストに舞台を作ってもらって、そこで鏡開きの装置で紙芝居を演じました。最後にマナの代わりに折り紙を切り抜いて作った魚を降らせたり劇の要素も入れて上演し、最後に英語のクイズも行ってみました。子供達は嬉しそうに参加していました。英国大使館とBritish Council共催のFestival UK ‘98の作品として取り上げられました。
――子どもたちはどうでしたか?
色々な病状のお子さんたちがいましたが、看護師さんとお医者さんに支えられて見ていた子が、私が「なんと、空から魚が降って来ました!」と言った瞬間、表情がパーッと明るくなって「降ってきた!」という顔になったのです。私はその時に、悲しいとかそういう自分の気持ちは吹き飛んで、何て素晴らしい経験をしたのだろうと思い、感激しました。初めての上演でしたが、プロの方に猫のダンスを振り付けてもらって、自作の歌も入れて話しました。そうしたら、自分ではそのようなことは全然思っていなかったのですが、お医者様が、治療を受けている方は、ハッピーな経験をすることによって幸せホルモンが出て、そのことが治療によい影響を与えると言ってくださいました。みなさんに喜んでいただけたことがとても嬉しかったです。
――全編英語なんですか?
主に英語でやっていましたが、大きな絵を見せながら、“Suddenly he saw a little boy! ”などというと、大体伝わります。子ども達は視覚的にお話を捉えていたのでしょう。
――その後も上演が続いたんですね。
はい。児童養護施設でも上演しました。猫のダンスを幼稚園の子どもたちと一緒に踊って楽しみました。皆上手でしたね。お魚をつかまえたり、子どもたちは、劇の中に入ってしまうんですね。その後、勤めていたBritish Councilでも上演することになって、ベトナムの子どもたちに文房具を送るためのNGOのバザーと合わせて、チャリティーショーでBritish Councilの先生方と共演しました。友だちのラジオパーソナリティにも宣伝してもらったりして、子どもの日ということで、菖蒲の花を持って、アフリカの曲をかけて、その時もダンスを踊りました。私はもともとダンスが好きでしたので。
――英語教育に、紙芝居の上演に、幅広い活動ですね。
私は、言語を通して伝えたい思いがたくさんあって、教室での英語教育と並行して、絵本を作ったりお話を書いたり、英語教材のメディアに声の出演をしたり、同時進行でやっていました。これは、以前アイデンティティで探っていた時に、自由に色々な自分を試みたらよいと思ったことと結びついていると思います。探ってみれば、自分ができる舞台、スペースがどこかにあるだろうと常に思っています。

紙芝居の猫のダンスを演じてみせてくださいました。
インタビュー後記
逸見先生、貴重なお話をありがとうございました。英語教育やボランティア活動の一つ一つに込めてこられた思いをうかがい、逸見先生ご自身が、英語・日本語という言葉、ダンス、声といった手段を自在に使う表現者でいらっしゃると感じました。そして、逸見先生の前では、誰もが安心して自分をオープンにし、よい表現者になれる気がしました。それは、言語の教育において最も重要なことであるように思います。この学びを今後ともCLERでの教育にいかしていきたいと思います。
インタビュー日時:2024年3月13日
文責:永澤済(言語教育研究センター准教授・広報委員)